秋の夜空に浮かぶ、大きくて丸い月を見ながらお団子をたべるお月見。
気が付けば当たり前のよう行われていたイベントですが、
「お月見って、なぜはじまった?」
「団子やすすきを飾る意味は?」と思ったことはありませんか?
お月見はお月さまを鑑賞するだけのイベントではなく、五穀豊穣や家族の健康を祈る意味があります。
本記事では、お月見の由来や歴史、昔から伝わる習わし、そして今風に楽しめる過ごし方など分かりやすく解説します。
お月見の由来は?簡単に解説
お月見の基本的な意味
お月見は、夜空に浮かぶ満月を眺め、その年の収穫できた喜びや五穀豊穣を祈る行事です。
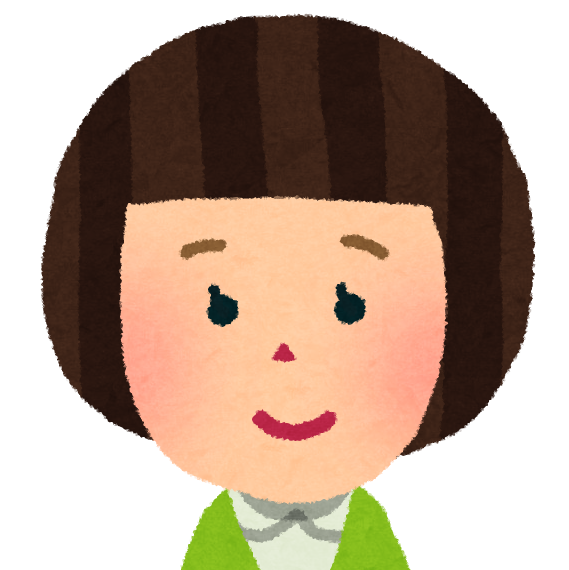
「中秋の名月」といわれる旧暦の8月15日(十五夜)は、一年のうちで月が一番きれいに見える日なんだって。
お月見は、月を観ながら「自然の恵みに感謝し、実りを喜ぶ」という大きな意味を持っています。
日本で広まった背景
中国では「中秋節」といわれる行事があります。
この風習が奈良時代に日本へ伝わり、平安時代の貴族たちが舟の上で和歌を楽しんだ「観月の宴」がお月見の始まりといわれています。
江戸時代になると、上流階級だけの行事だったお月見は、農村に広がり、秋の収穫祭と結びついて庶民の行事となります。
この時期から、お月見にお供えものをするようになりました。
お月見に欠かせない風習と意味
お団子の意味と数え方

お月見といえば、あの丸い「お団子」だよね!
あのお団子には何か理由があるのかな?
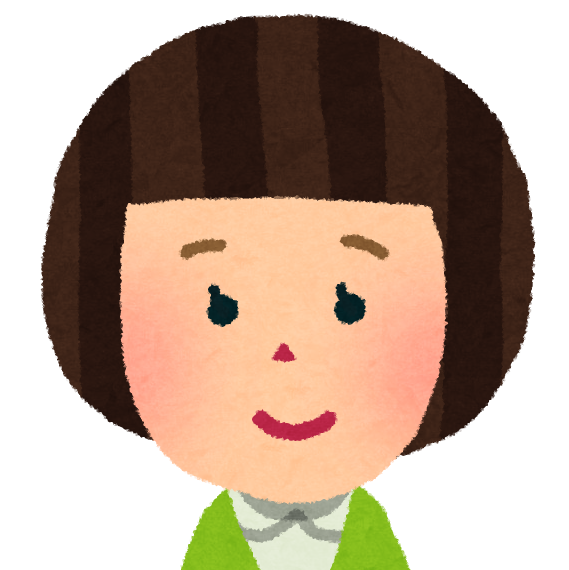
月見団子は満月の形と同じでしょ?
豊作への感謝や幸せを祈る意味があるんだよ!
用意する団子の数は地域によって違いがありますが、多くは「十五夜」にあわせて15個を積み上げるのが基本です。
しかし、1年が12か月なので12個だったり、十三夜に合わせて13個だったりする地域もあります。
月へ近づき、祈りが届きますように、とピラミッド状に高く積まれています。
すすきを並べる意味は?

お月見の時、すすきも一緒にお団子と並べて飾ってあるよね?
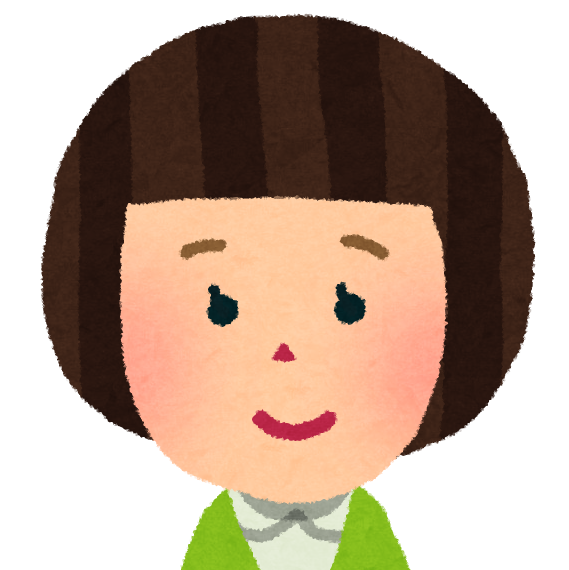
稲穂をお供えしたいところだけど、まだ稲刈りしてないからすすきを稲穂に見立ててお供えしてるよ。
また、すすきには魔除けの力があると信じられており、家を守るお守りの役割も担っています。
現在でも月見団子の横にすすきを奇数の数(1,3,5本)飾ります。
お月さまから見て左の方にすすき・芋類を、右の方にお団子を並べます。
月とうさぎの関係(民話・伝説)
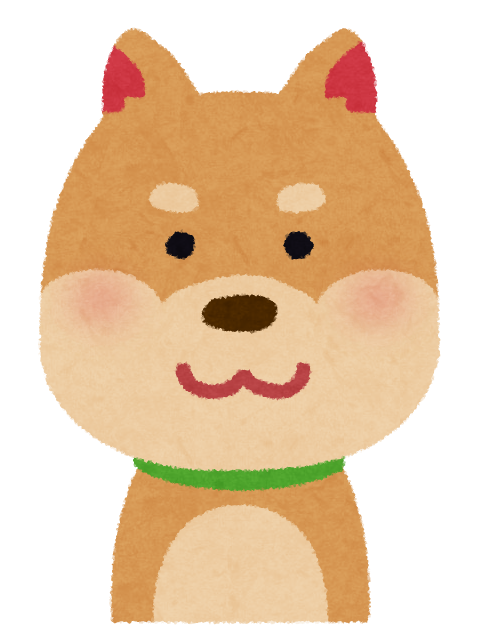
満月の中の黒い形って、うさぎが餅つきしてる姿に見えるよね!
お月見といえば「月のうさぎ」の伝説を思い浮かべる人も多いでしょう。
この切ない物語は仏教の説話がもとになっており、うさぎが自らの体をささげるほどの慈悲深さを表した話として伝えられています。月のうさぎは「優しさ」や「豊かさ」の象徴として、お月見と深く結びついています。
他のお供え物(里芋・栗など)
月見団子やすすき以外にも、秋に収穫した物をお供えします。
代表的なのは里芋です。「芋名月」という呼び名の由来にもなっていますね。ほかには、栗や枝豆、柿など季節の実りを供える地域もあります。
お供え物をして、自然の恵みに感謝しつつ、家族の無病息災や五穀豊穣の願いも込められています。
お月見の現代風な楽しみ方アイデア

家庭で楽しむ|ベランダや窓辺でお月見
広い庭や縁側がなくても、ベランダや窓辺から気軽に満月を観てください。月見団子や好きなお菓子を並べ、家族や友人と月を鑑賞しながらゆったり過ごすだけでも特別な時間になります。
照明を少し落とし、月明かりの中で静かな音楽をかけるだけで、いつもと違う雰囲気が楽しめます。
食で楽しむ|月見団子・和菓子・お月見メニュー
イベント事で楽しむといえば、食べ物は欠かせませんよね!
ごはんを丸く握ってみたり、たまごを満月に見立てた献立にすると気軽にお月見メニューが楽しめます。
スイーツはお決まりの月見団子のほか、ウサギをかたどった和菓子やブドウや柿などの果物を取り入れるのもいいですね。
最近ではファストフード店の「月見バーガー」やコンビニスイーツなどもありますよ!
子どもと一緒に楽しむ工作やアクティビティ
お子さんがいらっしゃる家庭では、お月見を学びの時間に変えるのも素敵です。
親子のコミュニケーションも深まり、楽しい時間が過ごせそう!
由来や意味を話しながら一緒に準備することで、楽しみながらお月見の意味を自然に伝えられます。
地域のお月見イベントに参加する
各地では「観月祭」や「月見コンサート」など、お月見に関連したイベントが開催されることもあります。
よく行く寺社や公園でも夜にライトアップされると、普段とは違った雰囲気を味わえます。過ごしやすい気候になっているので、歩いて回るのも気持ちいいです。
近年はオンラインで楽しめる「お月見ライブ配信」などもあり、自宅にいながら参加できるスタイルも人気です。
十五夜と十三夜ってなにが違う?

十五夜(中秋の名月)って?十三夜って?
お月見は2つあり、十五夜と十三夜と呼ばれています。
主に行われているものは十五夜になります。
| 十五夜 | 十三夜 | |
| 呼び名 | 中秋の名月「芋名月」 | 「栗名月」「豆名月」 |
| 発祥 | 中国由来 | 日本独自のならわし |
| いつ | 旧暦の8月15日 | 旧暦の9月13日 |
2025年のお月見はいつ?
2025年の十五夜(中秋の名月)は 10月6日(月) になります。
また、十三夜は 11月2日(日) になります。
お月見の日付は旧暦で決まるので、毎年、お月見の日は変わります。
きれいな満月を見るにはお天気も関係してきますが、日にちを確認し、前もってお月見のメニューや予定をたてておきましょう。
「両方楽しむのが縁起がいい」といわれる理由
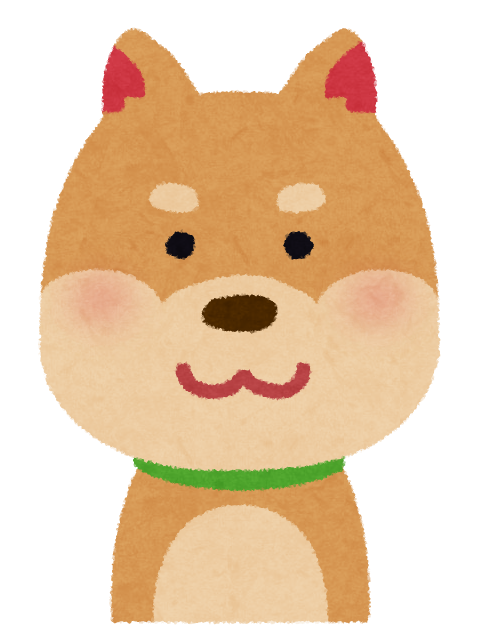
十五夜と十三夜の2日とも、きれいな月をみれたらいいことあるかも!
十五夜だけ、あるいは十三夜だけの片方のみを楽しむのは「片見月(かたみづき)」と呼ばれ、縁起が悪いといわれてました。そのため、昔の人は月見を2回行うようにしてきました。
縁起がいいならば、2回お月見をしたくなりますね。
お月見の豆知識
お月見にまつわることわざや言葉
日本には、月を讃えることわざや表現が数多く残されています。
たとえば「名月を取ってくれろと泣く子かな」は、子どもの純粋さを表現した俳句として有名です。
また、「月夜に提灯」という言葉は、明るい月夜に灯りを持つ無駄さから「必要のないこと」を意味します。
世界の月見文化の比較(中国・韓国など)
お月見はアジアを中心に広く行われています。
- 中国・・・「中秋節」と呼ばれ、家族で月餅を食べる
- 韓国・・・「秋夕(チュソク)」と呼ばれ祖先に感謝し家族で集まる
いずれも「月を愛でる」「収穫を祝う」「家族の絆を深める」といった共通点があり、家族で一緒に過ごし、楽しむようですね。
まとめ|お月見の由来を知り、楽しむ
お月見は、単に満月を観るだけのイベントではなく、長い歴史を持つ行事です。
団子やすすきには豊作祈願や魔除けの意味を持っていること、そして月のうさぎの伝説などを知ると、お月見が感慨深いものに感じられませんか?
今年のお月見は十五夜と十三夜の両日、お月見の由来を意識しながら、月を眺めてみてください。
風情を感じつつ、自分らしいスタイルでお月見を楽しめれば、秋の夜が特別な思い出になるはずです。
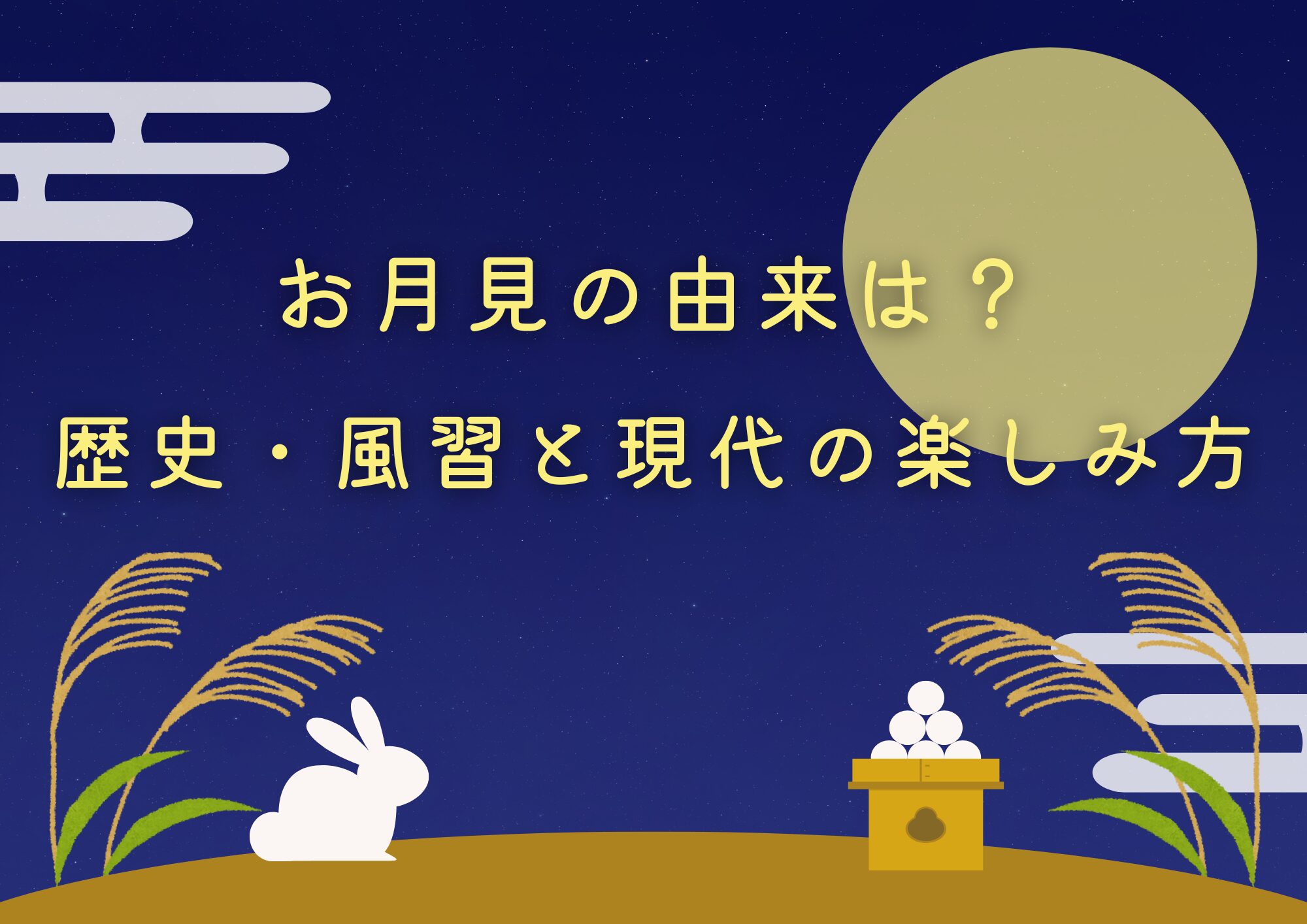


コメント